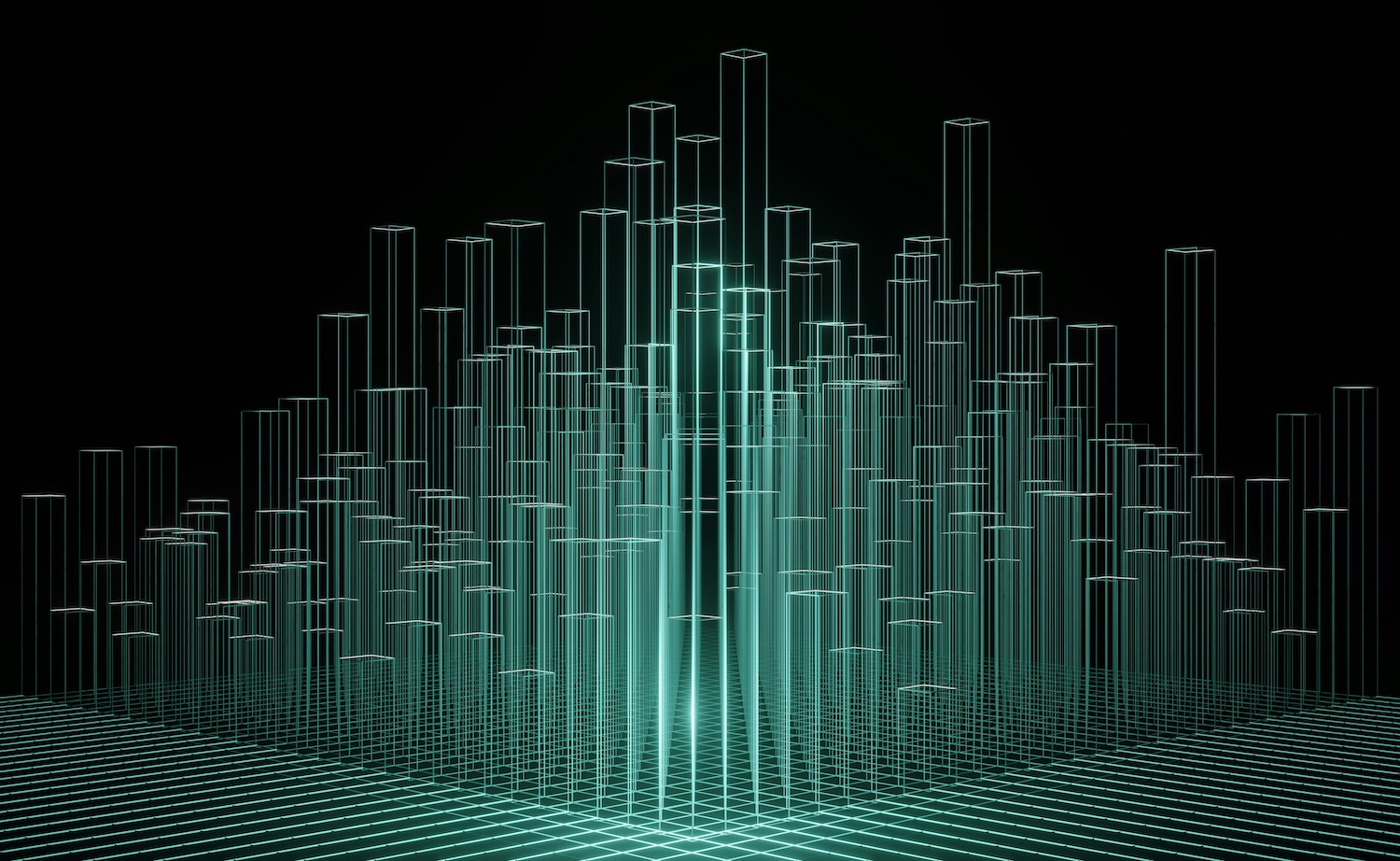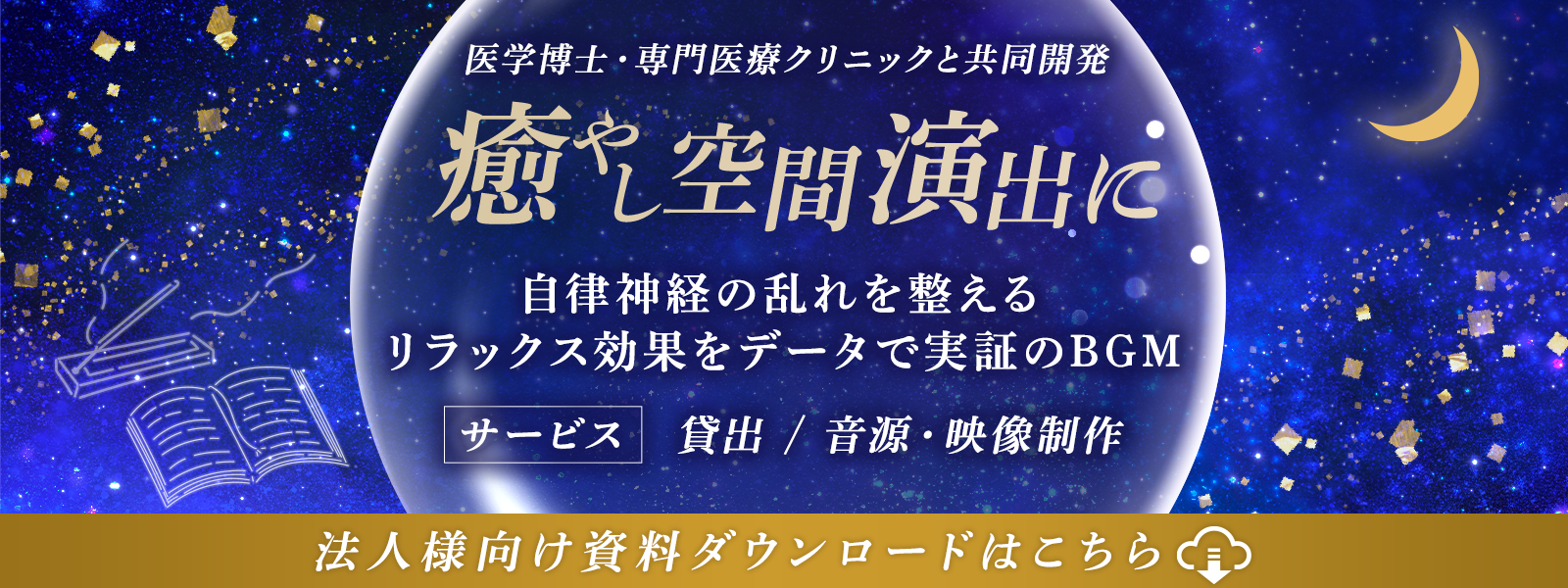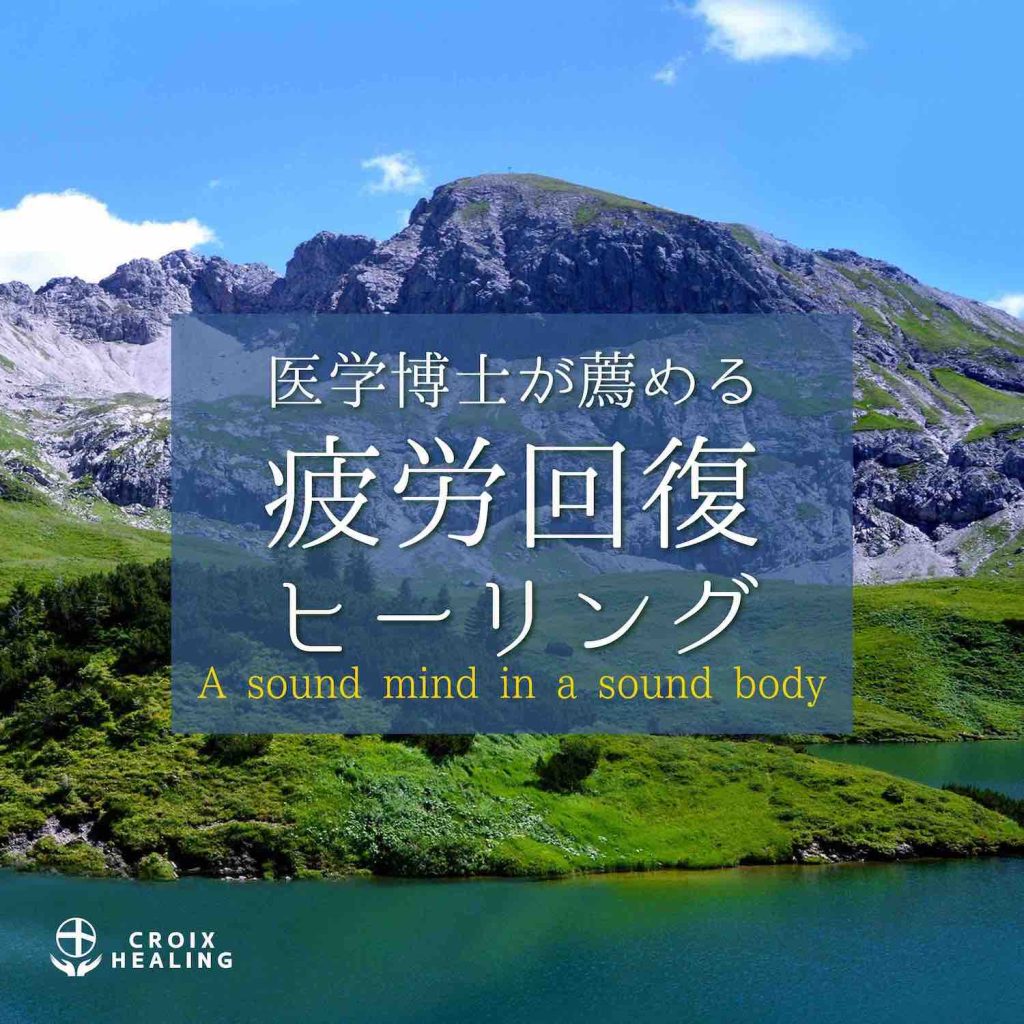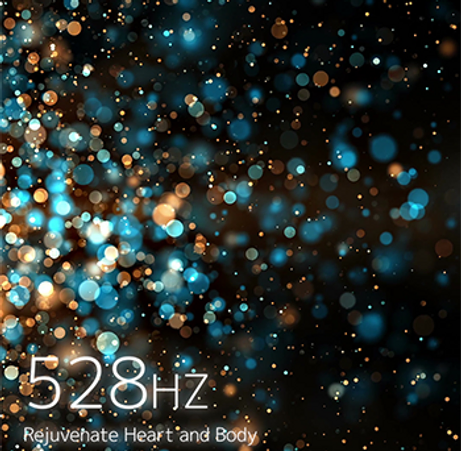医学博士で音楽療法士の板東浩です。
最近、会議続きで肩が凝り、夜は浅い眠りのまま朝を迎えてはいませんか。
慌ただしい毎日のなか、ふと「音に包まれて安心したい」と感じる瞬間があるかもしれません。
私たちは日々、知らず知らずのうちに“音”の影響を受けながら暮らしています。
従来、音響といえば左右のスピーカーによるステレオ再生が主流でしたが、近年注目されているのが「立体音響」です。頭上や背後からも柔らかな音が降り注ぎ、聴く人をまるごと包み込むように響いてきます。
この立体的な音の広がりをヒーリングミュージックに応用すると、脳はあたかも“音のコクーン”に守られているかのように錯覚し、呼吸や心の緊張がふっと緩む感覚が得られます。まさに、瞬時にリセットされるような体験です。
私もいくつか音楽作品の監修を行っているクロア社では、こうした立体音響によるヒーリング作品を多数配信しています。本コラムでは、それらの作品も紹介しながら、まずは自宅でこの安らぎを味わい、その感覚をオフィス環境にも応用していく方法を探っていきます。
立体音響は“安心ドーム”――音に包まれる生理学的メリット

360°の音がつくる包まれた安心感
立体音響は、別名「安心ドーム」とも呼ばれます。音が前後左右、さらに頭上や背後からも均等に届くことで、私たちの聴覚は全方位から包まれているような感覚を得ます。通常、聴覚は危険を察知するセンサーとして働き、周囲の音に対して警戒を向けています。しかし、全方向から自然で心地よい音が流れると、脳はその音環境を「安全」と認識しやすくなります。これは、安心感を生み出す音響的要素として極めて重要な特徴です。
警戒モードがオフになり、呼吸が整う
“安心”という感覚は、脳における扁桃体や視床下部などの情動調整系を介して、防御反応を穏やかに鎮静させます。その結果として自律神経系のバランスが副交感神経優位へとシフトし、呼吸は自然に深くゆるやかなパターンへ移行します。特に、横隔膜の可動域が広がり、胸式から腹式呼吸への切り替えが促されることで、換気効率が向上し、酸素分圧の上昇にもつながります。
また、呼吸のリズムが整うことにより、心拍変動(HRV)も安定しやすくなり、心拍と呼吸が協調する「呼吸性不整脈(RSA)」が強調されることで、心身が深い休息状態へと導かれます。この過程では、肩や首まわりに見られる持続的な筋緊張(特に僧帽筋や胸鎖乳突筋)も緩和されやすくなり、身体全体が徐々に脱力していきます。
音刺激がこの一連の反応を引き起こすのは、聴覚情報が大脳辺縁系および脳幹レベルでの自律神経制御中枢に直結しているためであり、リラックス音響は神経系と筋系の双方に対して調整的に作用することが、生理学的にも裏づけられつつあります。
没入感がもたらす、こころと身体のゆるみ
空間的な広がりと臨場感に富んだ音場は、感覚への心地よい刺激をもたらします。これにより、聴取者は音楽や自然音に対する没入度が高まり、心理的な安定が促されます。このような状態は、集中力の向上や情緒の安定に寄与し、不眠やストレスの軽減にも役立つ可能性があります。音による空間的な刺激が、脳と身体に調和をもたらす点で、立体音響はまさに“音のリラクゼーションツール”といえるでしょう。
全方位から音が降りそそぐ 360 Reality Audioによる音楽配信作品をご紹介
【360 Reality Audio とは】
360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)
「全方位から音が降りそそぐ、新体験。」
360 Reality Audioは、オブジェクトベースのソニーの360立体音響技術を使った新しい音楽体験です。
ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置。
アーティストの生演奏に囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場を体感できます。
詳細:https://www.sony.jp/headphone/special/360_Reality_Audio/
※360 Reality Audioは、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。
ちなみに、「響」という漢字は「音(おと)」と「郷(さと)」から成り、**“音が遠くまで届いて心に伝わるさま”**を意味します(引用元)。
現代の立体音響もまた、音が空間に広がり、心と身体の深部に“響く”感覚を与える点で、この古代の感性とどこか通じ合っているのかもしれません。
引用:おもしろ漢字辞典「響の意味・成り立ち・読み方・画数・部首を学習」
医学データが示す“ゆるみ効果”

三次元の音場がもたらす心理・生理的反応
頭上や背後を含む立体的な広がりを持った音は、私たちの聴覚を多方向から包み込み、脳や身体に心理的・生理的な変化を促します。特にリラクゼーションの効果が顕著で、心地よい音を聴取した際には、脳波においてα波が優位となり、ストレスの緩和や情緒の安定に寄与する可能性が報告されています。これは、左右方向だけの再生とは異なる、包囲されるような音響による反応といえます。
心拍リズムと自律神経系の調和
前後左右および上下から音が届く多方向性の音響は、聴覚に対して自然で滑らかな刺激を与えます。この感覚的入力は、中枢神経系を介して自律神経系に働きかけ、心拍リズムや呼吸に穏やかな変化をもたらします。特に、心拍変動(HRV: Heart Rate Variability)の解析においては、副交感神経活動を示すHF(High Frequency)成分が優位になり、交感神経とのバランスが整いやすくなる傾向が報告されています。
また、呼吸数の減少や心拍の一定化といった生理的指標の変化も確認されており、身体が「休息に適した状態」へとスムーズに移行していることが示唆されます。これにより、肩や首の筋緊張が緩み、無意識のこわばりが解放される過程で、「肩の荷がふっと下りた」と表現されるような深い安らぎを自覚することがあります。立体的な音刺激が、神経系と筋系の両面に穏やかな調整作用をもたらすことは、今後の音響療法の応用にもつながる重要な知見といえるでしょう。
空間認識の活性化と集中力の向上
周囲を巡る音刺激は、視覚と聴覚の連携を促し、脳の空間認知機能を活性化させます。たとえば、自然の環境音を立体的に再現する音場では、実際にその場所に身を置いているかのような感覚が生まれます。音の位置や方向を脳が処理しようとすることで、注意力や集中力が高まり、創造的な思考のベースが整えられていくと考えられます。
出典:立体映像・音響刺激が脳内血行動態、心拍および主観評価に与える影響
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje/51/Supplement/51_S338/_pdf
出典:音楽の本質に基づいた医療へのアプローチ
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmm/8/1/8_2/_pdf/-char/ja
出典:立体音響ARに基づくリラクゼーション支援システムにおける音源設置手法の検討
https://proceedings-of-deim.github.io/DEIM2023/5a-9-3.pdf

※全方位から音が降りそそぐ新しい音楽体験と4K映像によるスペシャルヒーリングミュージックビデオをお楽しみ下さい。( 👉 画像をクリック )
在宅環境における立体音響の応用

まずは「スマホ+イヤホン」で始める
音に包まれるリラクゼーション体験は、自宅でも手軽に取り入れることができますが、正確な効果を得るためには再生環境の整備が重要です。特に、音の広がりや定位感をしっかりと感じるには、専用の再生フォーマット(例:360 Reality Audio や Dolby Atmos)に対応したイヤホンやヘッドホンの使用が推奨されます。スマートフォンと対応デバイスを組み合わせることで、音が頭のまわりを巡り、一般的なステレオ再生では得られないような深い没入感を体験できます。
「呼吸が楽になる曲」を見つける
ヒーリング音楽は、立体音響や自然音を取り入れながら、心と身体がゆるやかに整っていくよう設計されています。副交感神経を刺激しやすい要素を中心に構成しているため、多くの方にとって、一定のリラックス効果が期待できる音として制作されています。
とはいえ、人の身体は千差万別。音への反応もまた、一人ひとり異なります。だからこそ、「自分にとって呼吸がいちばん楽になる曲」を見つけることが、セルフケアの第一歩になります。
医学的にも、深くゆったりとした呼吸や筋肉の緩みは、副交感神経が優位になっているサインとされています。たとえば、いくつかの楽曲を聴き比べながら、「今、息がしやすくなった」「肩の力が抜けた気がする」と感じられる瞬間があれば、それは身体が素直に反応している証拠です。
その感覚を覚えておき、繰り返し聴いていくことで、“この音を聴くと落ち着く”という反応が少しずつ育っていきます。これは、専門的に言えば「条件づけ」と呼ばれる現象で、音と安心感が結びついていく過程です。つまり、あなただけの“リラックススイッチ”が自然とできていくのです。
自分専用の“リラックス指標”をつくる
選んだ音源を繰り返し聴くことで、脳と身体は「この音=安心」という対応関係を学習していきます。とくに、呼吸が整い、身体全体がふっとゆるむような体験は、自律神経の調整を助ける「リラックスのサイン」として定着させやすくなります。
この指標をひとつ持っておくことで、日常のストレス場面でもその状態を再現しやすくなり、セルフケアとしての実用性が高まります。日々の中で“自分なりの楽さ”を明確に持つことは、メンタルの安定に向けた第一歩と言えるでしょう。
ドルビーアトモスの世界最先端サラウンドで立体音響体験が出来る作品をご紹介
【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。
【ドルビーラボラトリーズ】https://www.dolby.com/ja
※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。
おわりに
立体音響は、音による包まれ感を通じて心と身体の緊張をやさしくほどき、リラックスの状態へと自然に導いてくれます。まずは自宅で“音のコクーン”に身を委ね、自分に合ったヒーリング曲を見つけることが第一歩です。
そこで得られた感覚をオフィスでも再現することで、職場におけるリセットの習慣が生まれ、集中力や心の安定を取り戻しやすくなります。
静かな音の習慣が、働く日々の中にゆとりを生み、職場環境の整え方を根本から変えてくれることでしょう。
Supplement…
癒やしの映像と音楽でリフレッシュタイム・・・
RELAX WORLD『神秘の光』× 360 Reality Audio | 4K スペシャルヒーリングミュージックビデオ @RELAX_WORLD

アルコール0%の赤と白。本格風味と睡眠の質向上・・・
ワイン好きのための新感覚のウェルネスドリンク
「CHILLNEKO(チルネコ)」
本格風味を楽しみながら睡眠の質向上をサポートする新時代のウェルネスドリンクです。大麦発酵液のGABAをブレンドし、「機能性表示食品」の認証を取得。アンチエイジング、糖質制限、音楽療法、スポーツ医学などを専門とし、クロアのヒーリングミュージックの監修作品も手掛ける医学博士・板東浩先生と共同開発されたこのドリンクは、ワイン好きの方にもぴったりな心地よさと健康を両立させています。