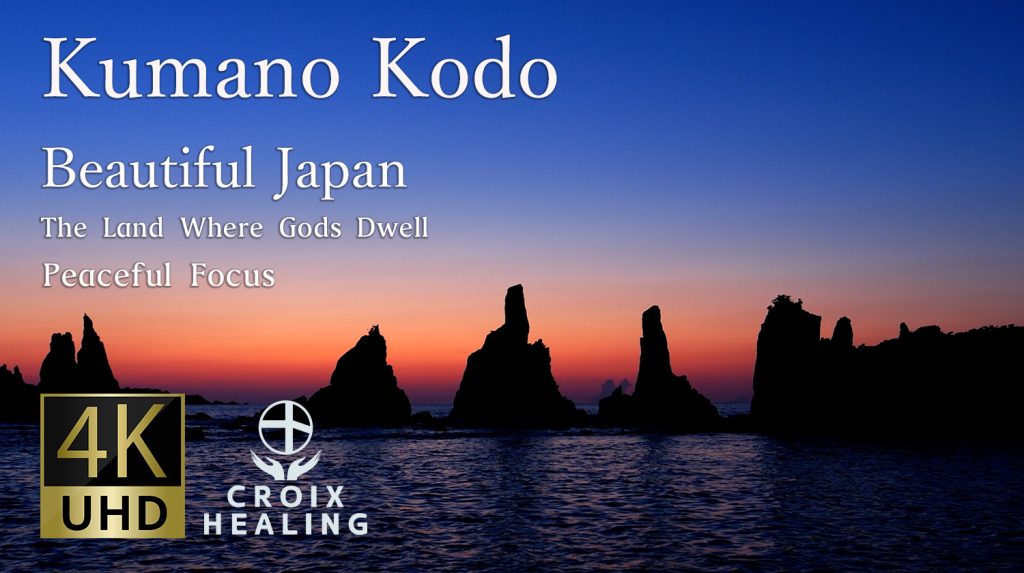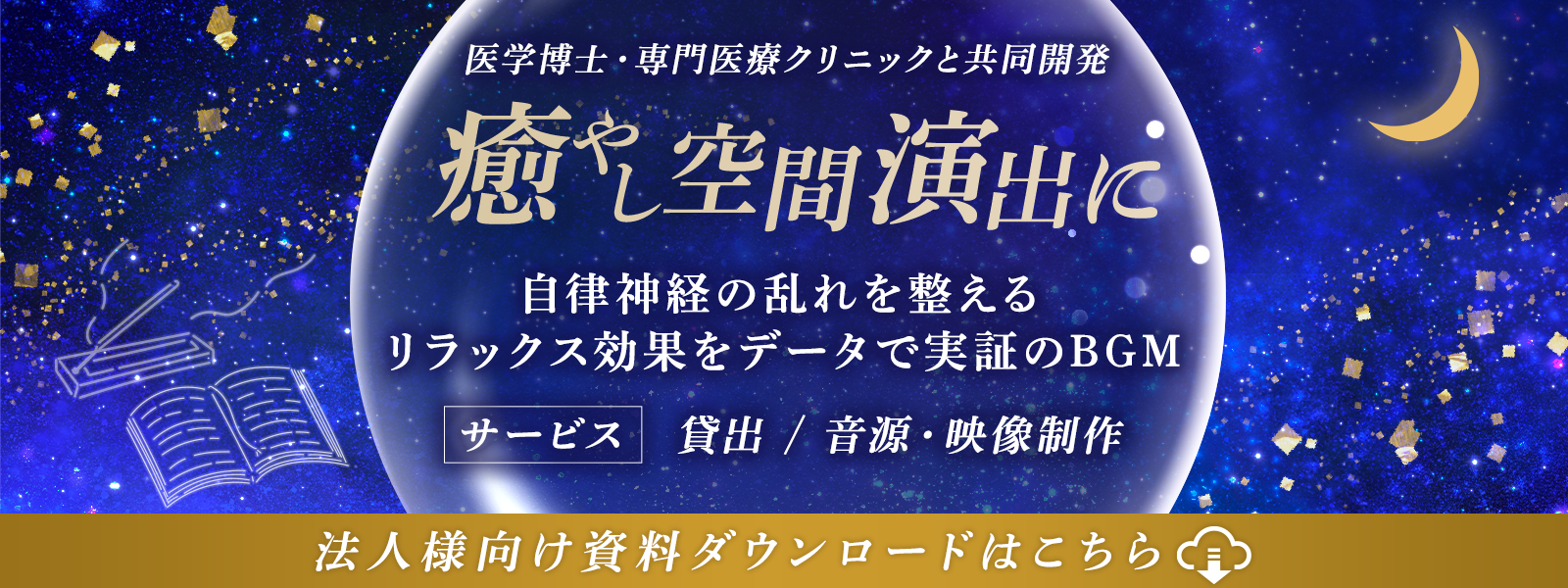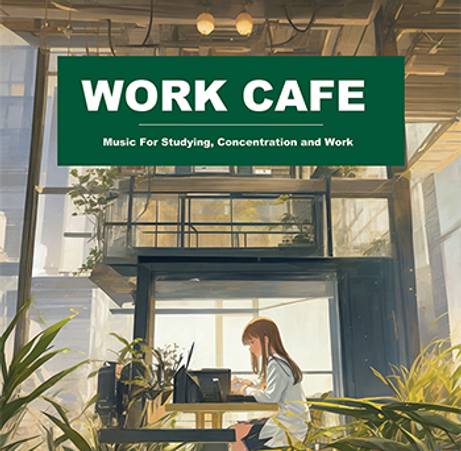医学博士で音楽療法士の
板東浩です。
リズミカルに進めたい仕事もあれば、
静かな集中が必要な作業もあります。
音楽は「効率を上げる環境デザインツール」
として活用でき、その効果は
“テンポ”によって大きく変わります。
本コラムでは、医学・心理学の視点から、
速いテンポの音楽が作業効率や集中力に
どのように作用するのかを
わかりやすく解説します。
音楽が身体に与える“テンポの力”とは?
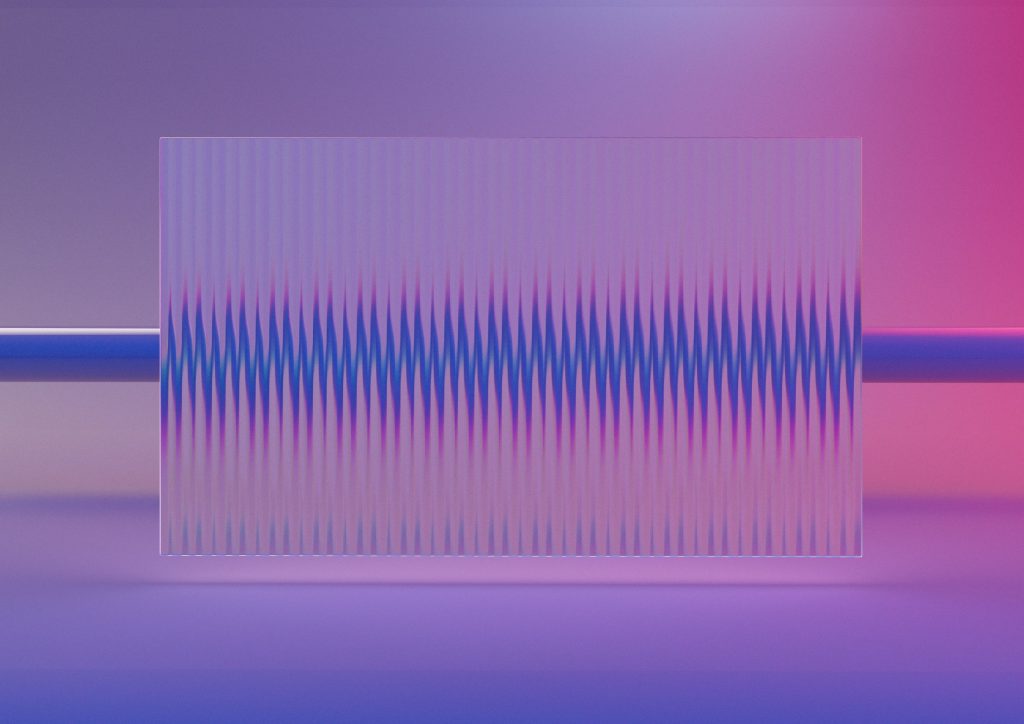
音楽が身体を動かす「BPM」の魔法
音楽の速さは「BPM(beats per minute)」で表され、
120〜140BPMは人の歩行や軽運動のリズムに近いとされます。
人間の身体は外部のリズムに自然と引き込まれる傾向があり、
これはエンタレインメント(entrainment)現象と呼ばれます。
心拍や呼吸、脳波までもが音楽のテンポに同調し、
無意識のうちに身体が動きやすくなるのです。
外部エンジンとしてのテンポ効果
例えば、屋内バイク(ペダリング)で一定のビートを聴くと、
脚の動きとリズムが自然にそろい、運動効率が上がります。
行進の120BPMやランニングの140BPMも同様で、
リズムに乗ることで持続力やスピード感が高まります。
この「外部エンジン」のような効果はデスクワークにも応用可能。
特に速いテンポは、作業ペースを自然に押し上げ、
単調な動作や繰り返し作業を後押しします。
テンポとは?
音楽の「速さ」を示す指標で、BPM(beats per minute)で表されます。
1分間に何拍あるかを数値化したもので、数値が大きいほど速くなります。
ー
・BPM(ビーピーエム):1分間に刻まれる拍(ビート)の数
・遅いテンポの例:60BPM(心拍と同じくらいのゆったりペース)
・中くらいのテンポの例:90〜110BPM(ウォーキングや軽い作業向き)
・速いテンポの例:120〜140BPM(行進、軽いランニングなど)
・とても速いテンポの例:160BPM以上(スポーツ、アップテンポの曲)
・身体や脳はテンポに自然と同調しやすく、これをエンタレインメント現象と呼びます
作業効率を高める“音の役割”

研究が示す3つの効果
カナダのLesiuk(2005)の研究では、
ソフトウェア開発者56名を対象に
BGMの有無を比較しました。
音楽を聴いたグループは
①効率の向上、②作業時間の短縮、③気分の改善
という3つの成果を示しています。
その理由のひとつは、
一定のテンポが作業ペースを安定させること。
さらに、BGMがオフィスの雑音をマスキングし、
集中を維持しやすくします。
脳を活性化する音楽の条件
心地よい音楽は脳内でドーパミン分泌を促し、
モチベーションや創造性を後押しします。
特に効果的なのは、
歌詞のないインストゥルメンタル音楽。
言葉の情報が脳の言語処理と競合しないため、
文章作成や読解など言語系タスクの集中を
妨げにくくなります。
逆に、歌詞付きの曲や極端に刺激的な音楽は
集中を乱すことがあります。
音楽の種類とテンポは、
作業内容に合わせて選びましょう。
出典
● Lesiuk, T.(2005年)
論文名:The Effect of Music Listening on Work Performance(心理学雑誌 Psychology of Music 誌掲載)
主な成果:音楽を聴きながら働いたグループでは、仕事のスピードや作業時間(time‑on‑task)、気分(positive affect)が優位に向上し、音楽なしの状態より全体的な作業効率が高かったとされています。
https://www.researchgate.net/publication/247733461_The_effect_of_music_listening_on_work_performance
「速い音楽」が合う仕事・合わない仕事
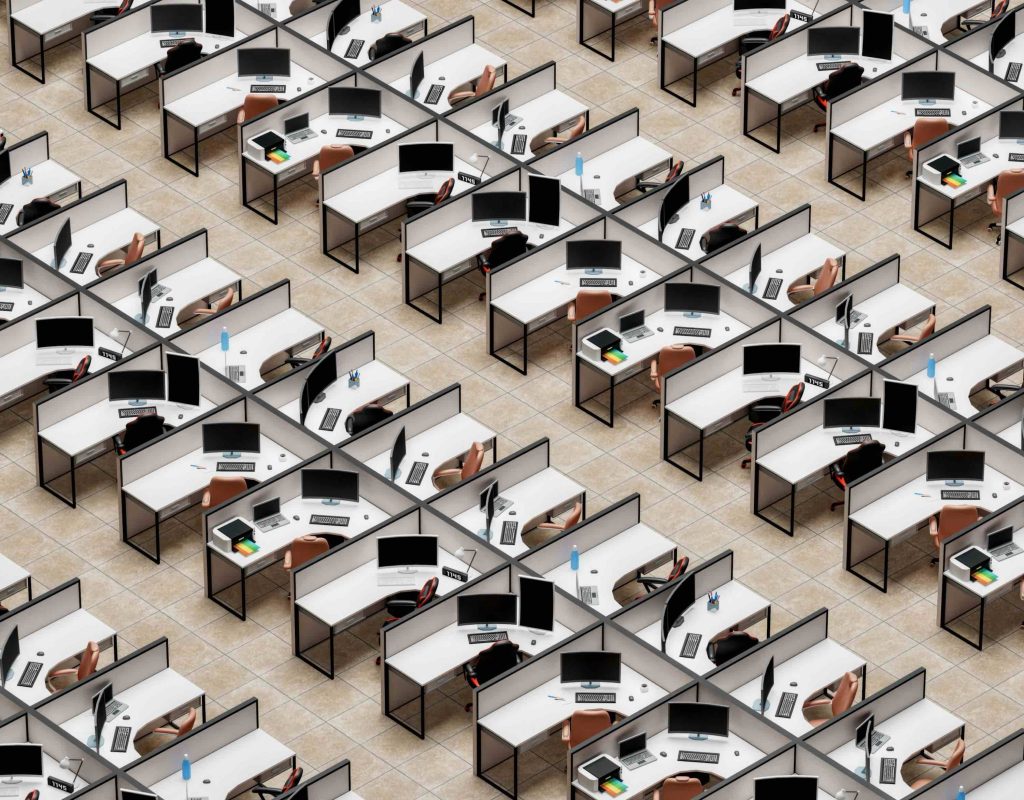
速い音楽が向いている作業
速いテンポの音楽は、
作業スピードと心の活性度を引き上げます。
そのため、データ入力や製造ライン、
ルーチンワークなど
リズムを保つ作業に向いています。
一定のテンポが自然と動作を加速し、
長時間の作業でも
集中を維持しやすくなります。
単純作業をリズムよく行いたいときには、ジャズやボサノヴァがおすすめです。
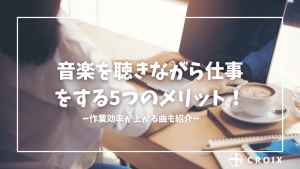
向かない作業と使い分けのポイント
文章作成や読解、分析、企画立案のような
高度な集中を要する仕事では、
速いテンポは逆効果になることがあります。
特に歌詞入り音楽は言語処理を妨げ、
正確性や思考の深さを損ねることも。
こうしたタスクには、
ゆったりとしたBPMや環境音、
静寂が適しています。
単純作業にはリズミカルな曲を、
思考系作業には落ち着いた曲を──
タスクに応じた切り替えが、
音楽を最高の環境デザインツールにします。

まとめ
速いテンポの音楽は、
外部エンジンのように心身を活性化させ、
単純作業や繰り返し動作の効率を高めます。
リズムが自然と作業ペースを押し上げ、
集中を長く保つ手助けをしてくれます。
一方で、文章作成や企画立案など、
高度な集中を要する作業では
逆効果になることもあります。
だからこそ、作業の種類や目的に応じて
テンポを使い分けることが重要です。
音楽は、効率と心の状態を同時に整える
“環境デザインツール”として、
日々の仕事に取り入れてみましょう。
Supplement…
癒やしの映像と音楽でリフレッシュタイム・・・
【熊野古道】神々が宿る地 「大辺路」と「伊勢路」 | @RELAX_WORLD